2001年2月1日
腫瘍学
おできの話
皮膚は体のすべてを覆い尽くし、わずかに目や口、鼻、肛門といったいくつかの天然孔に裂け目を作っているだけだ。体中の組織に占める割合も多く、外界からの刺激を和らげ、体温を保持する重要な組織なのだ。しかしまた、この皮膚という組織ほど、動物の種類によってさまざまに進化した組織はない。環境への適応ということなのだろうが、魚ではウロコとなり、亀ではコウラとなり、象の皮膚と人の皮膚が同じ物とはとても思えない。犬や猫の皮膚と人の皮膚を比べても、角化層の厚み、汗腺の数、皮下織の密度など、ずいぶんと様子が違う。従って、その皮膚に起こるトラブルもまた動物の種類によってかなり多様なのである。
次のカルテを手に取ると、問診票にはおできができたと記入されている。この「おでき」というのは曲者だ。人と同じように、毛穴の化膿つまり毛包炎のことももちろんあるのだが、何せ、プツッと何かができていれば、たいていは「おでき」と記入されている。関西弁では「でんぼ」ともいうが、最近の若い人には通じない。何かができているから「おでき」なわけで、これはもう何でも「おでき」でOKなのだ。
一般的に犬は体表の腫瘍の発生が多い動物だ。若い犬では、組織球腫というちょうどボタンのようなできものが顔の周りにできることがある。年をとれば皮脂腺の腺腫が多い。そのほか基底細胞腫や棘細胞腫など、これらはみな良性の腫瘍だ。腫瘍ではないいわばイボのようなものもある。しかし、肥満細胞腫や扁平上皮ガンなどの悪性腫瘍も少なくない。この肥満細胞腫はかなり厄介な代物で、FNAといって針で突いて細胞を見れば特徴的な顆粒が細胞質に見られ、あっさりと診断がついてしまう。しかし、悪性度の高いものではその時点で、肘にできていたなら「腕を落とす」位のアグレッシブな治療をしないととても命を助けられないのだが、それを理解してもらうのは、小学生に相対性理論を教えるより困難かもしれないのだ。確かに針で突いて顕微鏡をのぞいただけで、いきなり腕を落としましょうでは、この獣医は正気かと疑いたくもなる。延々と説明が続き、断脚を避けて、腫瘍の切除と化学療法の併用などの次善の策をとることもある。
悪いものではありませんようにと祈りながら診察室に入る。見ればなんとかわいいゴールデンの子犬ではないか! うっかり患者情報の年齢を見落としていた。これなら腫瘍年齢には程遠く、少なくとも悪いものではないと一安心。
「どこにおできができたのですか?」と聞くと、心配顔のオーナーは
「ここなんです。」とかわいらしいおちんちんの横を指差している。
ゴールデンは膿皮症の好発犬種だ。まして子犬ならおちんちんの周りに膿を持ったプツプツがたくさんできているのではと、良く見ると、皮膚はとても清潔できれいだ。
「はて、いったいどれのことですか?」と再度確認すると、その指先にはおちんちんよりもっとかわいらしい乳首があったのだ。確かに、人の感覚からすればおちんちんの隣に乳首などあろうはずもない。どうやって説明すれば恥ずかしい思いをさせずにすむだろうかと言葉を選びながら、
「それ、できものと間違える人がよくいるんですよ。」
さらっと乳首であることを告げながら、何食わぬ顔で「しつけと食事管理」に話題を変えたのは言うまでもない。
(文責:よしうち)
- 住所
- 大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7
- 営業時間
- 午前:9:00 〜12:00
午後:13:00〜15:00(水・土を除く)
午後:16:00〜19:00(水・土を除く)- ※祝祭日はその曜日に準じます。
- ※年中無休です。
- ※お電話、もしくは受付へ直接ご予約ください。
- ※ご希望の日と時間帯、獣医師を指定して頂くことができます。
- ※土・日・祝日に限り、予約料770円(税込)が別途必要となります。
- ※12/31〜1/3につきましては、12/30までに事前の予約確認が必要となります。
- 定休日
- 年中無休
- 最寄駅
- 大阪メトロ谷町線出戸駅もしくは長原駅
大阪市の南大阪動物医療センター
・・・新着情報・・・
- 2025.11.11
- 外来診療(予約なし診療)一部再開のお知らせ
- 2025.07.01
- 2026年度の新規採用募集を開始しました。
- 2025.06.06
- 満員御礼【キッズ獣医師体験会募集締切のお知らせ】
- 2025.06.04
- 45周年を迎えました。
- 2025.06.04
- 【キッズ獣医師体験会募集について、8/23はまだ空きがあります】
・・・診療時間・・・
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00〜 15:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16:00〜 19:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外来診療 17:30〜 19:30 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
- ※祝祭日はその曜日に準じます。
- ※年中無休です。
- ※お電話、もしくは受付へ直接ご予約ください。
- ※ご希望の日と時間帯、獣医師を指定して頂くことができます。
- ※土・日・祝日に限り、予約料770円(税込)が別途必要となります。
- ※12/31〜1/3につきましては、12/30までに事前の予約確認が必要となります。
・・・所在地・・・
〒547-0016
大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7
tel: 06-6708-4111
大阪メトロ谷町線出戸駅もしくは長原駅より徒歩8分








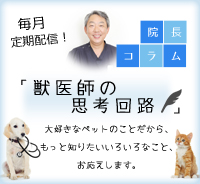
.thumb_200_auto_ka.jpg)



