2001年6月1日
泌尿器
よく水を飲む猫の話(その1)
猫は水を余り飲まない。うちにも3匹の猫たちがいるけれど、ペチャペチャ音を立てて水を飲む姿をたまに見かける程度である。飲み終えた後の器を見ても、水の量が幾分減っているのかなと感じるくらいのものである。
次の診察のカルテを手に取ると、武蔵丸くんの懐かしい名前がある。彼は一体何歳になったのだろうかと、生年月日を確認するともう14歳である。3歳くらいの時だったろうか、10階のベランダからスズメを取ろうとジャンプして、何とか地面に着地はしたものの、あの体重で10階の高さである、両肘を骨折してしまい、おまけに下唇はノドまで剥がれて垂れ下がっていた。その夜手術をし、しばらく入院した後、元のハンサムな顔と元気な体を取り戻して、意気揚々と帰っていったあの武蔵丸君である。カルテを繰っても、毎年の3種混合ワクチン以外、この歳まで病気らしい病気もせず、医者要らずだったようである。問診票に目をやると、「痩せてきた、元気が無い」とある。
診察室に入ってもらい、身体検査をしながら、問診を始める。あの若き日のはつらつとした武蔵丸君の姿は、今では白髪混じりの老猫の姿となり、診察台の上で居眠りを始めるのではないかと思うくらいにおとなしい。
「その節はお世話になりました。」のオーナーの挨拶のあとには、
「あれからずっと元気でほんとにいい子でしたが、もうずいぶん歳を取りました。」の言葉が続く。もう寿命なのかと問いたい気持ちがにじみ出ている。
「あの時は大変でしたね。」と、微笑み返しながら、
頭を撫で、眼球を見る。明らかに脱水なのだろう、眼球が落ち窪んでいる。そっと口を開けると、あの転落事故で抜け落ちた下顎前歯以外はきちんと揃っているが、歯茎の粘膜色は明らかに白っぽい。聴診器をあて心音を聴取する。心音はきれいで、同時に股動脈に当てた指に触れる脈拍ともきちんと同期している。
「食欲やウンチ、オシッコはどうですか?」
「特には変わりませんが、好きなものしか口にせず、ウンチは固め、おしっこは多いですね。」とのこと。背中をそっとさすり、皮膚を引っ張り、反対の手でおなかを触診する。弾力も毛艶もない背中の皮膚は、引っ張ったままの格好でテント状にその形をとどめてしまう。親指と中指で2つの円を描くように両の腎臓に触れる。左右ともマロングラッセほどの大きさしかない。
「それじゃ、水はたくさん飲むのですか?」
「そうですね、ずいぶん前から普通の猫よりは多いかなと思ってはいたのですが、そんなものかなと。どれくらいが普通なのですか?」
「余り飲んでいるところを見かけないくらいが普通ですよ。」
「それなら、普通のお茶碗くらいの水のみがしょっちゅう空になっているのは多いですよね?」
大量の水を飲み、それでも相当な脱水がある状況は、明らかに水和の異常である。大量の水分が失われているのである。
健康な猫では、水和は腎臓で精密に調節されており、その尿量は極めて少ない。しかし、これは、腎臓で濾過されている血液の量が少ないというのとは意味が全く違う。むしろ、日量数十リットルにも及ぶ膨大な量の血液が濾し出され、また同時に、ほぼ同じくらいの膨大な量の水分や体に必要なものが再吸収され、本当に不必要なものだけが数十ccの尿として排泄されているのだ。
武蔵丸君の腎臓は萎縮して、その再吸収能がほとんど無いのだろう。結果的に、彼の腎臓で濾し出されている血液の量は、尿量とほとんど同じくらいしかないはずである。つまり彼は、一日に約1リットルの水を飲み、彼の腎臓では約1リットルの血液が濾し出され、約1リットルの尿を排泄しているのである。健康な猫の数倍ほどの尿を排泄していても、数十分の1ほどの濾過量しかない。
人の腎不全では濾過能に問題が生じている場合のほうが多い。結果として、尿をつくれない、むくむ、吐き気がするなどの症状が出る。猫の腎不全では再吸収能に問題が生じてしまう。結果として、尿を大量に出し、脱水し、やつれてしまう。
一見正反対のようだが、腎臓での濾過量は共に極めて少なく、結果として尿毒症に陥ってしまうのである。
「武蔵丸君は腎臓がずいぶん衰えてきているようですね。」
「血液検査をして、現在の状況を正確に把握する必要がありますね。」
採血をし、通常のスクリーニング検査に水和パネル検査とさらにリンを追加してオーダーした。10分後には結果が上がってくる。
それまでに、腎不全についての長い長いレクチャーをしなければならない。
人にも猫にも、不老不死の薬は無いのだから。
(文責:よしうち)
- 住所
- 大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7
- 営業時間
- 午前:9:00 〜12:00
午後:13:00〜15:00(水・土を除く)
午後:16:00〜19:00(水・土を除く)- ※祝祭日はその曜日に準じます。
- ※年中無休です。
- ※お電話、もしくは受付へ直接ご予約ください。
- ※ご希望の日と時間帯、獣医師を指定して頂くことができます。
- ※土・日・祝日に限り、予約料550円(税込)が別途必要となります。
- ※12/31〜1/3につきましては、12/30までに事前の予約確認が必要となります。
- 定休日
- 年中無休
- 最寄駅
- 大阪メトロ谷町線出戸駅もしくは長原駅
大阪市の南大阪動物医療センター
・・・新着情報・・・
- 2025.06.06
- 満員御礼【キッズ獣医師体験会募集締切のお知らせ】
- 2025.06.04
- 45周年を迎えました。
- 2025.06.04
- 【キッズ獣医師体験会募集について、8/23はまだ空きがあります】
- 2025.06.01
- 【キッズ獣医師体験会のご案内】
- 2025.02.17
- キトンクラス始めました!
・・・診療時間・・・
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00〜 15:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16:00〜 19:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※祝祭日はその曜日に準じます。
- ※年中無休です。
- ※お電話、もしくは受付へ直接ご予約ください。
- ※ご希望の日と時間帯、獣医師を指定して頂くことができます。
- ※土・日・祝日に限り、予約料550円(税込)が別途必要となります。
- ※12/31〜1/3につきましては、12/30までに事前の予約確認が必要となります。
・・・所在地・・・
〒547-0016
大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7
tel: 06-6708-4111
大阪メトロ谷町線出戸駅もしくは長原駅より徒歩8分








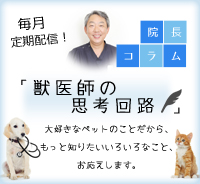
.thumb_200_auto_ka.jpg)



