2003年12月1日
循環器
心臓の話(その1)
「心臓に毛の生えたような人」とか「ノミの心臓」とか、心臓にまつわる言い回しは多い。けれど、その観念的な言い回しに反して、心臓の機能は実に論理的に説明される。
心臓の唯一にして重要な機能は血液を送り出すという機能である。そのために、心臓は充填のための心房と駆出のための心室に分かれ、心房は戻ってきた血液をドックンの「ドッ」で心室に送り込み、心室は充填された血液を「クン」で力強く送り出す。心房と心室はさらに左右に分かれ、右側は全身から戻ってきた血液を肺へ送り込み、左側は肺から戻ってきた血液を全身へ送り出す。それぞれ4つの部屋の出口には弁膜があり、血液の逆流を防ぎ、その血液の流れは純粋に流体力学的に説明される。さらにその血液を送り出す原動力となる心筋の収縮は、刺激伝導系と呼ばれる神経組織によって、心筋細胞のひとつひとつまでが緻密に電気的に制御されている。さらに、その刺激伝導系は、自律神経系の制御やアドレナリンなどの内分泌系の制御を受け、しかも、血液の流路である抹消の血管もその収縮の度合いを緻密に制御されているのだ。
この心臓の機能に問題が発生すればすなわち心臓病ということなのだが、少なくとも犬・猫における後天性心臓病は、人のそれとは大きく様相が異なる。
人の後天性心臓病では、心筋梗塞や狭心症などのいわゆる虚血性心疾患が大きな割合を占めるのに対し、犬では僧帽弁の逆流症と呼ばれるうっ血性の心疾患が、猫では肥大型心筋症と呼ばれる心筋疾患が、それぞれ大きな割合を占めている。
また、先天性心臓病では、動脈管の開存、右大動脈弓の遺残、心室中隔欠損、大動脈弁下部狭窄、肺動脈弁口狭窄などが比較的多い。
さらに、右心室から肺動脈にかけてソーメンのような虫が寄生するフィラリア症も心臓病のひとつと考えることもできる。
次のカルテはと手に取ると、マルチーズのミミちゃん10歳。最近、よく咳が出るとのこと。昨年のワクチン接種の時、聴診で心雑音がはじめて聴取されたという履歴がある。診察室に入ってもらい、身体検査を始めながら、
「咳はどんなときに出ますか?」と問いかけた。
「そうですね、家族が外から帰ってきてミミがはしゃぎまわった時とかに多いです。」
と、お母さん。
「去年のワクチンのときに先生から、咳が出たらすぐ来なさいと言われていましたので。」
実直さのにじみ出るようなお母さんの態度に、思わず頭が下がる。昨年の経緯はこうであった。
ワクチン接種の際に身体検査を行うのだが、聴診すると左側胸壁で心臓が収縮するときに「ザッ」という雑音が聞かれた。その1年前のワクチン接種時には聞こえなかったものだ。とうとうミミちゃんにもこの時が来たのかの感があった。雑音の聴取部位、質、犬種、年齢、全てが「僧帽弁の逆流症」を指し示している。僧帽弁領域に最強点があり、収縮期性の雑音で、中年以降のマルチーズである。この病気は遺伝性とする説が最も強く、中年以降に僧帽弁の弁尖に粘液変性が生じる。専門的にはベジテーションというのだが、しなやかな尾ひれのような弁尖にブツブツのイボができてきて、きちんと閉じることができなくなってしまう。きちんと閉じることのできない弁尖部のすきまから、血液の一部がもと来たほうへ逆流してしまう。その時の逆流音(渦流音)が収縮期性の心雑音なのだ。これは大問題である。
片時も休むことなく拍動を続ける心臓に生じた一点のほころびは、休むことができないがゆえに、その問題を拡大し続ける。僧帽弁は左心房の出口にある。肺で酸素を供給された血液は左心房へ戻る。そして左心房の収縮によって左心室に充填される。充填されるやいなや左心室は強く収縮しその血液を全身に向けて送り出す。この時に作り出されるのが収縮期血圧なのだが、その圧に僧帽弁は耐え左心房へ血液が戻って来ないようにしている。普通の人の血圧が収縮期で130mmHg位とすると、水柱ではその13.5倍=1755mm=約1.8m、つまりホースに穴をあけると人の背ほどまで水が吹き出す圧力ということになる。その圧が弁尖のすきまにかかり、左心房へと流れ込む。左心房はこの逆流した血液と肺から戻ってくる血液で満員電車状態となり、拡張を始める。拡張した左心房は真上にある気管支を持ち上げ咳が出始めるということになる。少なくともこの時点で左心房の負荷を減らす薬を開始せねばならない。このままの状態では、次第に左心室にも拡張が生じ、肺にもうっ血が現れ、最終的に心臓全体が内圧に負けてパンパンにストレッチしてしまい、肺水腫、呼吸困難へと坂を転げ落ちていってしまう。
こんな風に、ミミちゃんのお母さんと昨年に説明したことの復習をした。そして、現在の心臓のコンディションをみるためにレントゲン検査と心エコー検査を実施させていただくことになった。
レントゲンでは確かに左心房の拡張があり、心臓の横径も少し大きくなっている。エコー検査では、僧帽弁に肥厚とイボの形成が確認でき、左心房の径は通常の1.3倍ほどになっている。Mモードで左心室の内径の短縮率を見ても50%に近い猛烈な勢いで収縮している。さらにカラードプラをかけると左心室の収縮時にみごとな逆流のモザイクフローが左心房へ吹き込んでいる。お母さんにミミちゃんが検査台の上で横になっているのを手伝ってもらいながら、エコーの画面を指差して説明する。
「間違いなく僧帽弁の逆流症ですね。」
フリーズをかけて弁尖にできたイボを見てもらう。そして、左心房に逆流するカラーフローを見てもらう。
「左心房は大きくなってきてますね。本当はこれくらいの大きさなんです。」
そういいながら、本来は大動脈基部の横系と同じ位なのだと説明する。
「左心室もこんなに一生懸命収縮して血液を送り出さなくてもいいはずなのですが、逆流がある分余計に仕事をしないと全身に送り出す血液の量が足りなくなりますから、普通のワンちゃんよりもずっと強い収縮をしているんです。」
「幸いなことに、三尖弁には逆流はありません。」
エコー検査を済ませ診察室に戻って、左心房にかかる負荷を減らすためのお薬が必要なこと、特に咳止めなどは用いなくとも拡張した左心房が少し小さくなってくれるだけで咳は止まっていくことなどを説明した。
実際、ACE阻害薬が開発され、動物医療に用いられるようになって、僧帽弁逆流症のワンちゃんの寿命は飛躍的に延びた。何より、ジギタリスと利尿薬だけの治療時代と比べ、この病気を持っているワンちゃんの生活の質も格段に向上した。けれども、決してそれが原因治療でないことだけは理解してもらわなくてはならない。弁尖の異常は弁尖を取り替える以外に根治法はないが、わずか2kgのミミちゃんの弁尖を取り替えるのは非現実的な話と言わざるを得ない。
僧帽弁逆流症は、最後にはミミちゃんの命を奪ってしまうに違いない。けれども、その最後の日が来るまでには、まだまだたくさんの思い出を家族みんなと作れるに違いない。そのために十分な時間と十分な生活の質を提供することが、ミミちゃんやその家族に対する自分の使命なのだ。
「このお薬で当分の間は何事もなく生活できるようになると思います。けれども、僧帽弁の問題が解決したわけではありません。体のもついろいろな調節の仕組みをお薬でやりくりして、心臓にかかる負担を減らしているのです。僧帽弁の状態そのものは少しずつ進行して、またやりくりのつかない日が来てしまいます。その時には利尿薬やそれ以外のお薬も処方しなくてはなりません。少しでもその日が来るのを遅くして、天寿と呼べる年令まで一緒に暮らしていただきたいと思っています。そのためにも、お薬はきちんと忘れずに、そして、塩分と強い運動は避けてください。」
実直なミミちゃんのお母さんのことだから、きっとマメに管理していただけて、5年後にはまだまだ元気というのも夢ではない。定期健診にもきちんと来て頂けるに違いない。
「ミミちゃん、人生はまだまだこれからだもんね。」
少しも若々しさを失っていないミミちゃんに、励ましの言葉をかけずにはいられなかった。
(文責:よしうち)
- 住所
- 大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7
- 営業時間
- 午前:9:00 〜12:00
午後:13:00〜15:00(水・土を除く)
午後:16:00〜19:00(水・土を除く)- ※祝祭日はその曜日に準じます。
- ※年中無休です。
- ※お電話、もしくは受付へ直接ご予約ください。
- ※ご希望の日と時間帯、獣医師を指定して頂くことができます。
- ※土・日・祝日に限り、予約料550円(税込)が別途必要となります。
- ※12/31〜1/3につきましては、12/30までに事前の予約確認が必要となります。
- 定休日
- 年中無休
- 最寄駅
- 大阪メトロ谷町線出戸駅もしくは長原駅
大阪市の南大阪動物医療センター
・・・新着情報・・・
- 2025.02.17
- キトンクラス始めました!
- 2024.07.29
- 満員御礼【キッズ獣医師体験会募集締切のお知らせ】
- 2024.07.20
- 【キッズ獣医師体験会のご案内】
- 2024.07.01
- 2025年度の新規採用募集を開始しました。
- 2024.03.01
- 2024年4月1日~ 料金改定のお知らせ
・・・診療時間・・・
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00〜 15:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16:00〜 19:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※祝祭日はその曜日に準じます。
- ※年中無休です。
- ※お電話、もしくは受付へ直接ご予約ください。
- ※ご希望の日と時間帯、獣医師を指定して頂くことができます。
- ※土・日・祝日に限り、予約料550円(税込)が別途必要となります。
- ※12/31〜1/3につきましては、12/30までに事前の予約確認が必要となります。
・・・所在地・・・
〒547-0016
大阪府大阪市平野区長吉長原3-5-7
tel: 06-6708-4111
大阪メトロ谷町線出戸駅もしくは長原駅より徒歩8分








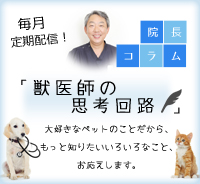
.thumb_200_auto_ka.jpg)



